仏壇と厨子

今回は【仏壇と厨子の違い】についてお話しします。
「厨子(ずし)」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれません。
けれども歴史の教科書に出てきた「奈良県法隆寺 玉虫厨子(たまむしのずし)」を思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一見、仏壇と似ていますが、実は成り立ちや役割に違いがあります。
厨子とは?
厨子の歴史は日本に仏教が伝わった時と同じ飛鳥時代とされています。
仏像や大切な物を納める箱で木や漆塗りで美しいものが多かったそうです。
奈良の「玉虫厨子」はその代表例で、鮮やかな装飾と精緻な造りで知られています。

玉虫厨子(たまむしのずし)
飛鳥時代(7世紀ごろ)に作られた仏教の厨子で奈良・法隆寺に現存しています。
日本における仏教美術の代表作のひとつで、国宝に指定されています。
形は小さなお堂のような姿で扉を開けると、中に仏像を安置できるようになっています。
「玉虫」の緑や紫のキラキラとした輝きのある羽を背板や装飾部分に貼り付けて装飾し、非常に豪華でした。
仏壇との違い
仏壇は、家族みんなで仏さまをおまつりする場所です。仏像だけでなく、ご先祖さまや亡くなった方をしのぶ祭壇としての役目もあります。
それに対して厨子(ずし)は、もっと小さなもので、ひとりひとりが使うことが多いです。仏像や位牌(いはい)のほかに、お守りや思い出の品など、大事なものを入れる箱として使われます。
また、厨子は大きな仏壇の代わりとして、仏像や位牌をおまつりする、簡単なお仏壇のような役目をすることもあります。
現代では、ペットの供養や小さな仏像を安置するために用いられることもあり、お仏壇よりも柔軟な使い方ができます。


現代に生きる厨子の魅力
仏壇と比べると厨子はコンパクトで場所を選ばず、マンションや洋室などにも取り入れやすいのが特長です。
当社でお作りしている「仙台厨子」は、仙台箪笥と同じ伝統の技を生かしており、重厚感と高級感を兼ね備えています。
リビングや書斎に置いても自然に調和し、現代の暮らしに合った新しい祈りのかたちとして人気です。

仏壇と厨子の違い
仏壇=家、家族でご先祖様を供養する場所
厨子=個人単位で仏像や守り本尊を納めるための箱(仏壇に比べて用途はより広くなります)
歴史的にも深い意味を持つ厨子は、時代を超えて人々の心に寄り添ってきました。
ご家庭の暮らしや祈りのかたちに合わせて、仏壇と厨子のどちらを選ぶか考えてみるのも良いかもしれません。
👉 次回は【お仏壇を置く場所について】をお届けします。どうぞお楽しみに。
カタログ請求&オンラインショップのご案内
仙台仏壇をじっくり比較したい方は、ぜひ無料カタログ請求をご利用ください。
無料カタログには、仙台仏壇のラインアップとサイズ一覧、仕上げやデザインのイメージを掲載しています。
また、オンラインショップでも主要モデルをご覧いただけます。
気になる商品があれば、ページ内の詳細サイズや画像をチェックし、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
仙台仏壇をもっと知りたい方は
どんなことでもお気軽にご相談ください。
➡オンラインショップを見る https://www.sendaitansu.jp/SHOP/231569/216671/list.html
➡カタログ請求をする https://www.sendaitansu.jp/top/catalogue/
➡ショールームへ行く https://www.sendaitansu.jp/top/showroom/
➡仙台仏壇の納品事例を見る https://www.sendaitansu.jp/top/album/sendai-butsudan/
➡公式Instagramをチェック https://www.instagram.com/keyakisangyo.official/

- 監修者
- 相澤 裕子







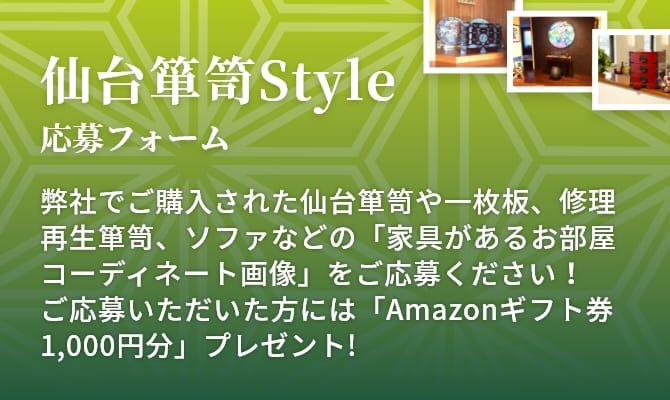

仙台駅から徒歩8分。仙台箪笥のモデルルームを併設した仙台東口ショールームにて営業担当しております。 長年この仕事に携わってきた経験を活かし、お客様一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます。 仙台箪笥や仙台仏壇のことなら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。